| 『いんたあふぇいすを跨いだら、男の子は少女になっていた。』 テーブルに数冊並べて置かれた単行本の帯には、そんなアオリ文句が踊っている。 ランドセルを背負って歩く男の子の影が、呆然と立ちすくむ少女の姿へとつながっていくイラスト。 大書きされた『いんたあふぇいす』のタイトルと、著者名「微風ろろみ」。 『尋ね人騒動の“ろろみちゃん”が書いた』とそのものズバリのコメント。 あらたまったように一階上の会議室に通されて、否応もなくそんな表紙を見せ付けられる。 「あんたの本なんだよ」と、正世が後押しするように囁いた。営業さんが「おめでとうございます、微風先生」と続ける。 作家になったんだ。今更ながらに実感が胸の奥から湧いて出てくる。 雑誌に作品が載ったときにも、会見やその後の取材のときにも、授賞式のときにも思ったことだけれど、今回がいちばん。 「どうもありがとうございます。すごくいい表紙です」 「何度も打ち合わせをした甲斐があったね」 編集部で表紙デザインの打ち合わせをしたときには、ろろみはもっと抽象的なイラストの案を推していたが、正世と原島、さらにS伸一郎の主張に折れて、こちらの案を通した。 けれども本になったものを見れば、この表紙でよかったと思う。 自分の描きたかったストーリー世界だけでなく、自分自身の心境を的確に表していて、そして見る人へのインパクトも大きい。 S伸一郎たちのほうがろろみ当人よりも、この作品をどう売り込むかについてよく理解していたのだろう。 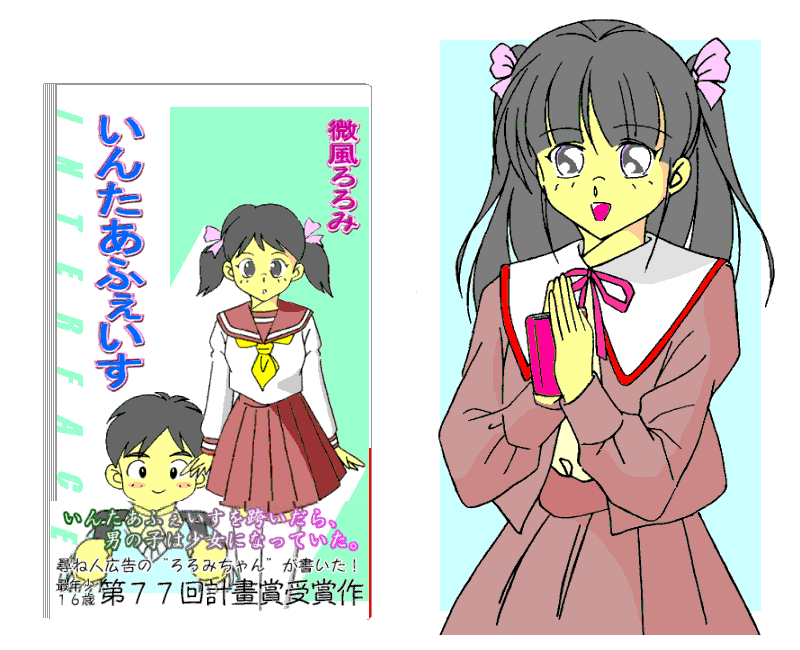
そんな本を囲んで、ろろみは正世、そして計画書店の営業さんと三人、『いんたあふぇいす』発売記念サイン会の打ち合わせに入る。 思えば正世にスカウトされる直前、ろろみは絵崎たるとのサイン会会場に足を踏み入れていた。そのときの感慨もあって、単行本が出たらサイン会をやりたいというのはろろみの予ねてからの希望だった。 しかも会場になる書店はそのときと同じ店。ろろみがそうしてほしいと頼んだわけではないが、奇遇とも言い切れない。こういうアイドル作家のイベントに強い店は数店に限られているのだ。 営業さんの話によると、書店で五百枚用意した整理券がわずか十五分で捌け切ったらしい。さすがろろみ。行列に並ぶ順番はサイン会当日の抽選で決まるので、早く来たから早い順番がとれるわけではないのだが、それでも始発で来店しないと間に合わなかったようだ。 ところが、いよいよ当日進行についての打ち合わせに入ろうとしたとき、正世の口調が不意に優しくなった。 「ろろみ、最後に確認しておくけど、本当にサイン会やっていいの?」 「……どうしたんです、いったい?」 「あんた、コンビニ強盗とか授賞式のハプニングとかいろいろあったでしょう。サイン会なんて不特定多数が集まることやって、怖くないのかなって思って」 「えっ、なに?」 「中止してもいいんだよ。ろろみ当人が顔を出さない、ただのサイン本配り会にするって手もあるよ。どうする? これが最終確認」 ろろみのデリケートな心に、正世は気を遣ってくれているのだ。計畫賞発表のときの厳しい態度とは大違い。 けれども今のろろみの目には前しか見えていなかった。 営業さんが同席している。もう整理券も配ってしまった。ここで予定を変更すれば、お客さん、書店さん、営業さん、みんなに迷惑をかける。 どんな客が目の前に立つかわからないサイン会に、不安がないわけではない。けれどもろろみはその不安を振り切った。これまで自分は、いくつも困難を乗り越えて成長したではないか。今回もまた、成長する様をファンのみんなに見せよう。それもアイドル作家・微風ろろみらしさではないのか。 ろろみに、アイドル作家としてのプロ意識が根付いていた。 「何言ってるんですか! やりますっ! ぜったいっ! あたしが本配ります。握手もしますから」 机をバンバンと叩く音が、ろろみの熱弁の伴奏になった。 すると正世は大きくろろみに肯いてから、営業さんに顔を向けた。 「ほらね、この子の迫力、言ったとおりでしょ」 ろろみがサイン会を断念するはずがない。それを承知で、正世はろろみをノセようとあんなことを言ったのだ。 「……なんか、正世さんの手の平からは絶対出られないって感じ」 |