| 部屋の目覚し時計が、珍しく朝方に鳴った。眠気を振り切らんとベッドの中で体をねじらせる伸一郎に、枕もとに置かれた大小二つのカバンが、本当の意味での二重生活が幕を開けることを告げていた。 両親にはバイトが昼番だからと言っての、早い外出。慣れない満員の通勤電車に揺られ、いつもの地下鉄駅に着く。計画書店の最寄り駅だ。けれども今日は、そして今日から二年間は、別のところに向かうためにこの駅を使うことになる。 P伸一郎がいつもの多目的トイレでスプリットすると、ろろみは普段着のトレーナーにデニムパンツ姿。昨日の夜、リンクアップする前に着ていた服装と同じである。 確認しておくと、リンクアップしたときのスプリット体(ろろみ)の服装がペアレント体(P伸一郎)に記憶され、次にスプリットしたときにはスプリット体はその服装で出現するのだ。 向かって立つS伸一郎は落ち着かない様子だ。なにしろ今日は、ろろみの新しい服装を見ることができる日なのだから。S伸一郎が待ちきれずに大きいほうのカバンのファスナーを引くと、ベージュ色のそれが姿を覗かせた。 「ろろみちゃん、さあさあ早く着替えて」 どうせ着替えないといけないことはわかっている。けれどもやたらと急かせるS伸一郎に、ろろみは声を荒立たせた。 「言われなくても着替えるさ。そんなに早く見たかったなら、昨日リンクアップする前に、明日は公園でスプリットしようって言えばよかったんだ」 「でもな、定期がまだだからここまでひとりで来て倹約しようって言ったの、ろろみちゃんのほうだろう」 「あっ、そうか」 今は、S伸一郎のほうに分があった。 「とにかく着替えるから、早くここから出ろよ」 「わかった。でも、学校じゃそんな言葉遣いはダメだよ、ろろみちゃん」 「わかってるって、さあ」 S伸一郎をトイレから追い出してひとりになったところで、ろろみは大きく腕を伸ばして深呼吸をする。 実はろろみ自身が、S伸一郎に負けず劣らず落ち着かなかったのだ。この少女の裸体を見ることにはもう慣れている。そうではなく、学校の制服を着るというのが照れくさいのである。 もとは二十五歳の青年だから、高校卒業まで制服を着ていたとしても七、八年ぶり。照れるのも致し方ないことだ。 おまけに伸一郎の場合はさらに上を行く。学校の制服というものを着た経験が幼稚園のときしかない――そのほかの制服にしてもバイトで着るコンビニの制服くらいだった。小学校は公立で私服。中学高校は私立の男子校だったが、そこは割と自由な校風のため制服がなかった。自主的に学生服を着ていた同級生も何人かいたけれど、伸一郎がその輪に加わるタイプのはずもない。つまり、伸一郎は約二十年ぶりに、実質的には生まれて初めて、制服を着て登校するのである。 ろろみとして編入試験を受けに来たときにも、校内で何人もの生徒とすれ違うたびに、自分もこの服を着るのかと思いつまされた。好奇心もあるけれどもそれ以上に照れくさい、というか恥ずかしい。制服を着て街中を歩くのは頭の上に赤い回転灯を乗せて周囲に警戒色を振りまくようなことだと思えてならなかった。 もちろん伸一郎のまわりには制服のある学校の生徒たちがたくさんいる。彼ら彼女らはああいう服を着てよく平気でいられるのか、必死に我慢しているのか、それとも慣れてしまえばなんとも感じないのか、伸一郎は中学時代からずっと不思議に思い続けていた。その考えは、時には制服への妙な好奇心へと転じることもあった――編集部でろろみの高校編入の話を最初に聞いたとき、どんな制服なのかを声を上ずらせて尋ねてきたS伸一郎のように。 伸一郎の両親は学生運動華やかなりし時代に高校生活を送り、制服廃止を叫んでいたという――だからふたりの息子も制服のない学校に進ませたのだろう。伸一郎もそんな両親の心境を、どの程度かはわからないが、自分のものの一部にしていた。 もっとも、もうひとりの伸一郎、トイレの外でろろみの着替えを待っているS伸一郎は違う。こうしたP伸一郎の過去の想いについての記憶がないらしく――されど制服への好奇心はしっかり受け継いでいるというのが面白いものだ――ろろみの高校編入も所詮は他人事なのだからと、ろろみが制服姿で扉を開けて出てくるのを今か今かと待ち構えているのだ。 そういう伸一郎としての過去はともかく、“水明華高校の生徒・微風ろろみ”となったからには観念しなくてはならない。トレーナーと下のTシャツ、ボトムのパンツを脱いだろろみは、再度の深呼吸で覚悟を決めてから大きいカバンに手をかけた。 まず取り出したのが純白の丸襟ブラウス。よそいき服のブラウスとは違って無地でフリルなどの飾りもないけれど、それゆえに袖を通そうとするだけで緊張する。 次にえんじ色のリボンを慎重に首へとまわす。結び目がもうできあがっていて、首の後ろでホックで留めるタイプのリボンなのだが、留めてみると首が締められるようにきつい。こんな窮屈なものをつける日々を想像すると、高校編入への後悔の念がちらりと頭をよぎる。けれどもすぐに思い直した。一度外して長さを調整すればよかったのである。するとちょうどいい感じになった。 スカートは無地のベージュ色でボックスプリーツタイプ。上着はファッション誌のモデルでも着た覚えのあるボレロタイプで、ボタンは首もとのひとつだけである。どちらも布地――サージという名前らしい――が堅く、袖を通すと今まで着てきた女ものの服とは重みが大分違うとわかる。伸一郎は一年に数回くらいだが男物のスーツを着ることがあるが、それともまた異なる皮膚感覚だ。否が応にもこれが制服なのかと意識させられる。 ボレロのボタンの上にさっき留めたリボンを出しながら、今まで見ないように努めてきたトイレの中の鏡へとゆっくり目を向ける。そこでろろみは、ただの少女から女子高生に“変身”した自分に文字通り直面させられた。 なんというとんでもない姿に。それが鏡の中のろろみへの第一印象だった。外見に嫌悪感を覚えたのではない。制服姿でもろろみの魅力はいささかも失われていなかった。思わず吸い込まれそうな透明度の高いすまし顔。目と口をにっこりと緩めてみれば、相変わらず弾けるろろみスマイル。そこに、ブレザーやセーラー服タイプとは違った、明るい色調ながらも質素で落ち着いたボレロタイプの制服が加わることにより、少女の幼さとあどけなさが強く醸し出され、ろろみらしさを一層確立させていた。 とんでもない。それは畏怖の心境だった。そして、こんな自分を外に曝すことへの照れくささだった。 ろろみはそれに加えて、学校制服が似合いすぎる自分が悲しくさえ思えてきた。伸一郎が幼稚園以外で着たことがないしもう一生着るはずのないものに、この十六歳の少女はどうしてこんなにもフィットしてしまうのか。 そう考えるとなぜ悲しいのかが見えてくる。なぜ“変身”なのかもわかってくる。ろろみは自覚したのである。ろろみ自身に内在するものが原因で、自分がまたワンステップ、P伸一郎との距離を広げてしまったことを。リンクアップすれば伸一郎に戻れるとわかっていても、今の自分がこうであることへの慰めにはならないのだ。 ろろみは、テレビや雑誌の撮影で着た衣装にもこんな想いを抱いたことはなかった。アイドル作家といってもマスメディアでは基本的にタレントではなく文化人として扱われる。だから、フリルいっぱいのお姫様ドレスだの、超ハイレグのレオタードだの、いかにも撮影用のサテン地がてかてか光ったセーラー服だのといった、恥ずかしそうな奇抜な衣装を着せられることはなかった。ろろみは基本的に私物の服――もちろんよそいき服だが――でマスメディアに出演していたし、ファッション誌のモデルのときも着た服はオーソドックスなものばかりだった。仮に奇抜な衣装を着せられていたとしても、ろろみ=伸一郎にはこの学校の制服のほうがよほど恥ずかしく思えたろう。 ふとろろみは現実に返った。待っている人がすぐ外にいる。ここは躊躇せず、女子高生アイドルを演じるしかないのである。 ろろみは洗面所の水で顔を濯ぎ、一昨日買ったばかりのレースのハンカチできれいに水を拭き取り、大小ふたつのカバンを片手に持ちながら、トイレの引き戸にもう片方の手をかけた。 「待たせちゃったね、シン」 溌剌とした声とともに、明るく健康的だが落ち着きのとれた女子高生が現れた。ろろみにはもうさっきの逡巡のかけらもない。 「すごーい! 思ったとおり似合ってるよ」 S伸一郎が目をまるくして制服姿をほめた。ろろみの思ったとおり。 「ありがと。素直に受け取っておくね」 今のろろみは、S伸一郎――そして、かつてのP伸一郎――の考えていた理想の女子高生像に最も近い存在なのだから。中身がP伸一郎なのだから当然かもしれないが、ろろみはさらに意識してそれを演じるよう心がけていた。 伸一郎は屈み込みながら、なめまわすようにろろみの全身を観察している。制服姿がそれだけ珍しいのだろう。 当然、ろろみは愉快ではなかった。一見して変態のような行為を“伸一郎”がしているのもいい気分ではない。けれども我慢できた。面と向かわないのならば、自分自身を目にすることにも慣れてきていたのだ。せめて今は伸一郎を喜ばせてあげようという、アイドルとしてのサービス精神も働いている。そしてなにより、S伸一郎の制服への興味の根はさっきのろろみ自身と同じところにあるのだし。 ふたりの横を出勤途中のサラリーマンたちが速足で通り過ぎていく。誰もがちらちらとこちらに目をやるが、慌しい朝ゆえかそれ以上のことをする者はない。 「シン、これくらいにしましょうよ。不審人物って思われちゃうよ」 「そうか。学校の時間だってあるしな……そうだ」 ろろみが足を出口に向けようとすると、伸一郎は慌てたようにろろみと逆方向に走り出す。そして売店で立ち止まる。三十秒後、伸一郎は使い捨てカメラを片手に戻ってきた。 「早く気づけばよかった。……家にマイカメラがないのって悲しいよな」 「なるほど。初登校記念写真ならあたしもほしいもの」 だれが見ているかわからないので、ろろみはスイッチを女言葉に切り替えていた。 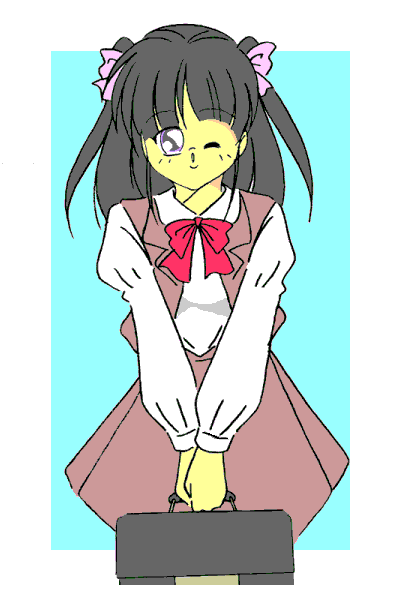 階段を上がり地上に出て、通い慣れた計画書店ビルを背にして歩き出す。
階段を上がり地上に出て、通い慣れた計画書店ビルを背にして歩き出す。しばしばビルの谷間で立ち止まる伸一郎から、ろろみは幾度となく使い捨てカメラのフラッシュを浴びせられた。歩いている途中を不意に撮られた写真もあれば、ポーズをとらせられた写真もある。通学カバン――先ほどの小さいほうのカバン――を両手に持たされてみたり、腕時計を見ながら――口にトーストはないけれど――慌ただしく走る姿勢をさせられたり。 「さすがにもう時間ね。急ぎましょ」 「大丈夫。フィルムもうなくなったから」 「それ早すぎ!」 ふたりは、少しだけ歩調を速めながら水明華高校への道を進んだ。 周りを見わたすと、スーツの海の波間から紺のセーラー服や緑のブレザーがときどき浮かび上がってくる。このあたりは都心に近いとはいえもとは文教地区で、ビル街の谷間にいくつも学校があるのだ。 ろろみたちも速足だというのに、右を白襟のセーラー服が、左を派手なチェックのブレザーがすたすたと追い抜いていった。 「それにつけても、いろいろな学校の制服があるよな」 「シンは、この制服どう思う?」 「大好きに決まってるじゃないか。ろろ……キミにすごく似合ってるから」 「そう言うと思ってた。あたしは……地味なデザインなんだけど目立っちゃうところが、正直言って好きとも嫌いともいえないな」 セーラー服はあの襟とラインですぐそれとわかるし、ブレザーの制服は最近ではチェックやらエンブレムやらで派手に飾ったものが多い。それらに比べると、水明華高校のこの制服は、可愛らしいけれど少し主張が弱そうなボレロ。制服としては珍しいタイプだから、その意味では目立つのだけれど。チェック柄やらエンブレムやらといったアクセントがない点ではやっぱり地味といえるが、明るいベージュ色が周囲に強くアピールしている。 ろろみは、そんな制服をまだ持て余していた。 「地味だけど目立っちゃうか。そういうところもキミらしいんじゃないかな」 「……そうかもね」 さっきよりは少し明るい口調で、ろろみは答えた。 |